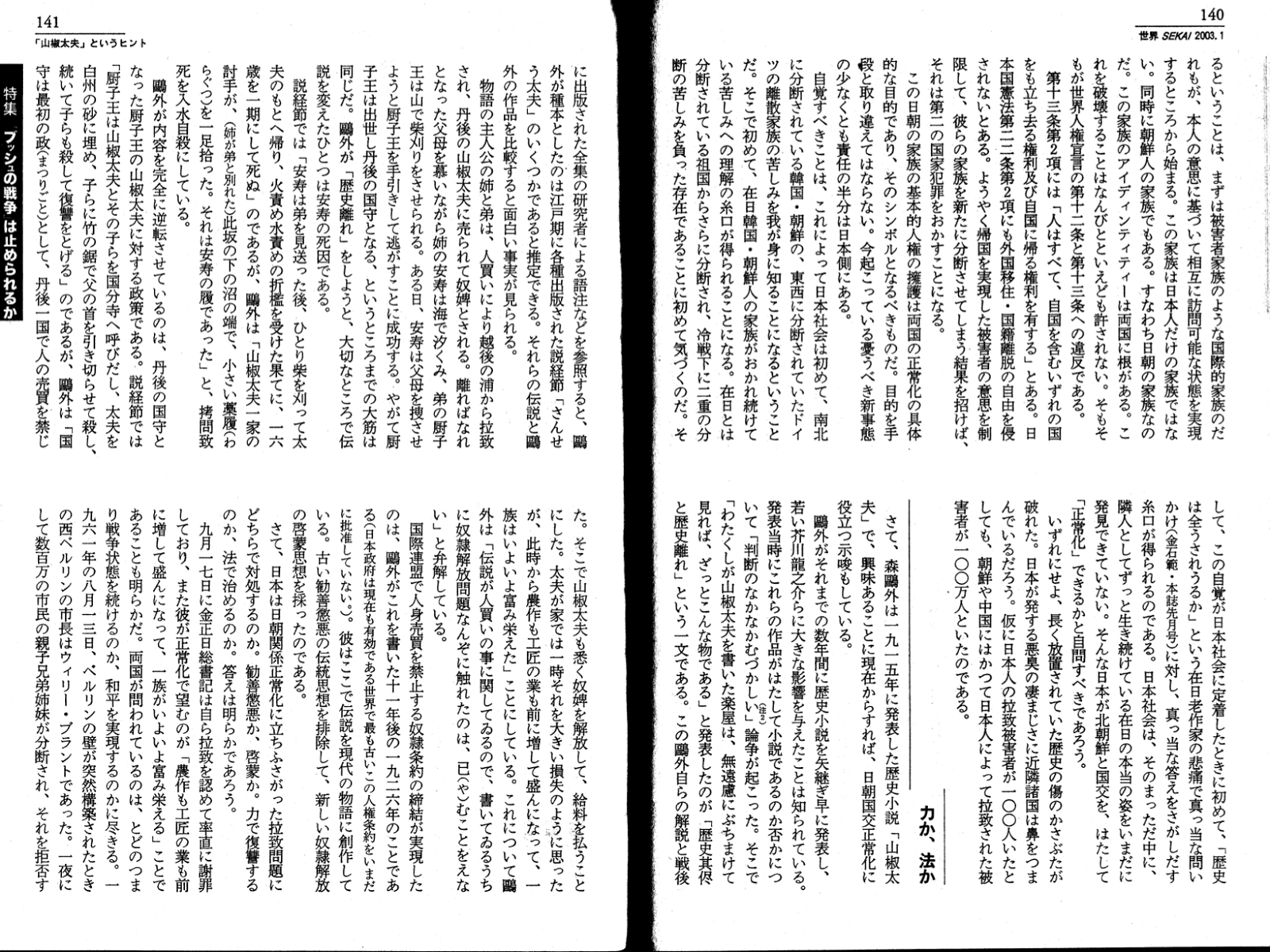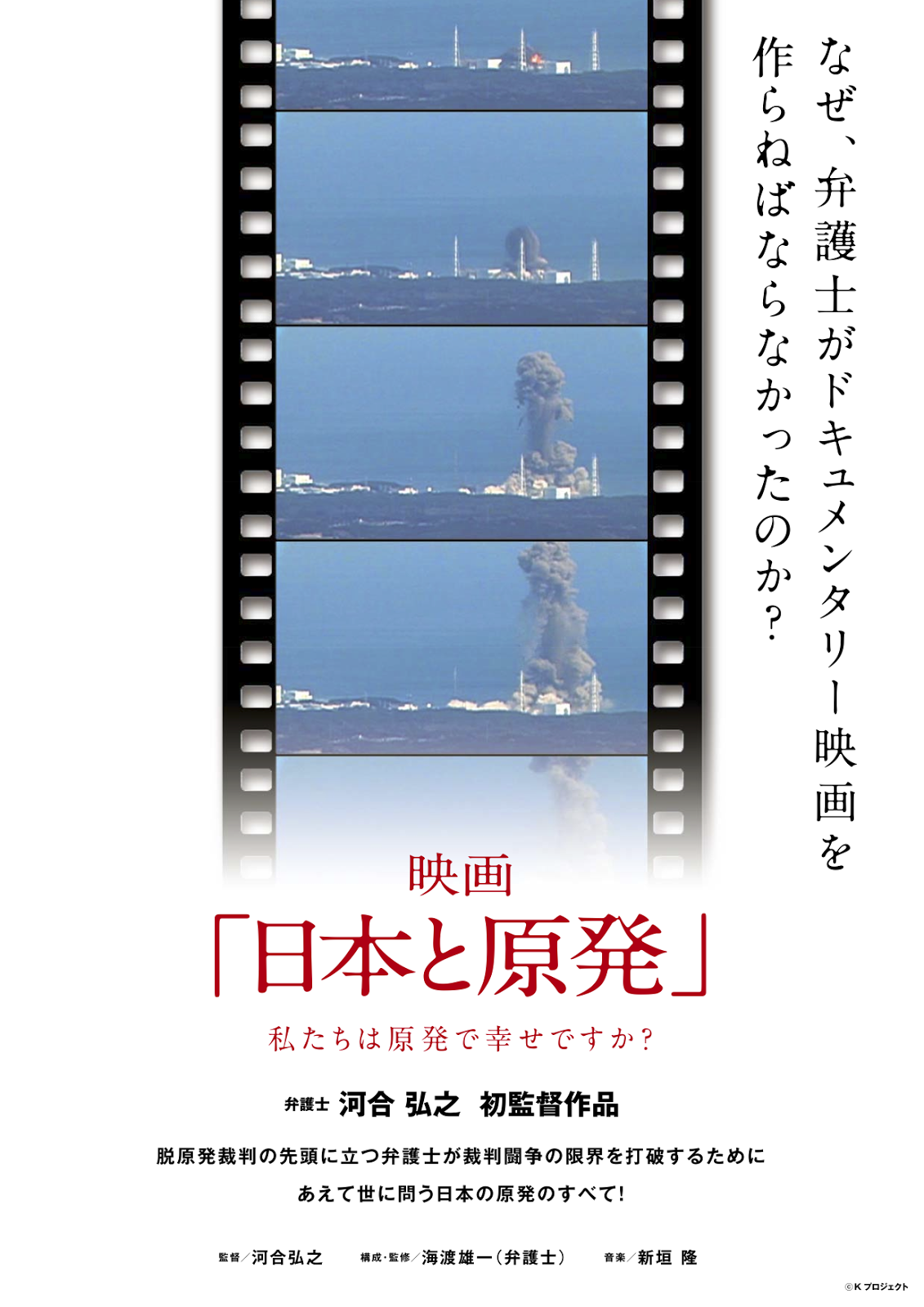以下に紹介されているサイトの監督の言葉からも判るように、若くして日本へ留学した班忠義監督は、中国の遼寧省撫順の生まれです。
彼の故郷は日露戦争の時代から日本が進出、良質な黒炭など地下資源の埋蔵が豊富であるために長い間日本の支配下におかれました。特に軍国主義日本が武力で「満州国」をでっち上げて以来、戦前から軍部によって「日本の生命線」とされた「満州国」の資源の中枢でした。したがって、撫順を故郷とする日本人は少なくありません。例えば、つい最近亡くなった山口淑子(中国名:李香蘭)さんも1920年撫順生まれです。
彼女の人生も美貌もあって波乱に満ちたものでしたが、生まれ故郷が同じ班忠義さんが、日本で中国帰国子女の問題から、日中戦争開始以来はここも豊富な石炭など地下資源を確保するために侵略の拠点とした山西省における日本軍の性暴力問題を知り、その多くの犠牲者の中に山西省一といわれた美貌の女性がおり、彼女を知る犠牲者たち、さらには元日本兵の加害者の証言を長年の努力で作品としたことは、わたしには単なる偶然とは思えません。
最近も「慰安婦」問題が未解決のために、日本政府の歴史認識が国際社会からも厳しく問われています。この映画を見ると、この問題が、第二次大戦中の日本兵による性暴力の実態が、すでに日中戦争時からどのような凄まじい構造を持っていたかを、当事者たちの映像証言で知ることができます。この作品を見たら、いわゆる「慰安婦」とされた人たちが受けた暴力がどれほど非人間的なものであり、決して無視したり忘れてしまってはならない事実の重さを知ることになります。そのようなことは、日本人として恥ずべきことです。
このことをはっきり示唆した出来事が最近日本の皇居でありました。先月末日本を国賓として訪問したオランダのアレクサンダー国王は、天皇の晩餐会での挨拶で次のように述べています。日本のメディアはちゃんと伝えないので、オランダ王室の公式記録に実際に述べた英語とオランダ語とオランダ語の原文がありますので、該当部分だけを訳出しておきます。
---------------------
So we will not forget - cannot forget - the
experiences of Dutch civilians and soldiers in the Second World War. The wounds
inflicted in those years continue to overshadow many people's lives. Grief for
the victims endures to this day. Memories of imprisonment, forced labour and
humiliation have left scars on the lives of many.
Zo vergeten wij ook niet - zo kunnen wij niet
vergeten - de ervaringen van onze burgers en militairen in de Tweede
Wereldoorlog. De wonden die in die jaren zijn geslagen, blijven het leven van
velen beheersen. Het verdriet om de slachtoffers blijft schrijnen. De herinneringen
aan gevangenschap,dwangarbeid en vernedering tekenen het leven van velen tot op
deze dag.
私たちは第二次大戦中におけるオランダ市民と兵士の体験を忘れようとは思いませんし、忘れることはできません。この数年間に負わされた傷の痛みは、多くの人々の人生に暗い影を投げ続けています。犠牲者への悲しみは今日も続いているのです。拘禁と強制労働と陵辱の記憶が多くの人々の人生にいくつもの傷跡を残しているのです。
--------------------ここで国王は「性奴隷」と具体的に述べて這いませんが、スマラン事件などの日本軍の強制売春の犠牲者を抱えるオランダ国王の言葉として示唆するところは明らかです。 すなわち、当時の体験は天皇と国王といえども無視と忘却が許されない、痛みが今も続く事実であるということです。
天皇も晩餐会招待の挨拶でまずこのように述べています:
「このように長きにわたって培われた両国間の友好関係が、先の戦争によって損なわれたことは、誠に不幸なことであり、私どもはこれを記憶から消し去ることなく、これからの二国間の親善にさらなる心を尽くしていきたいと願っています。」
この席には安倍晋三首相をはじめ、内閣閣僚も列席して聴いていたはずです。彼らは史実にまったく無知なので痛くも痒くもないのでしょう。これを無恥といいます。
前置きが長くなりました。以下が映画と監督とのトークの案内です。めったに得られない機会ですので誘っておいで下さい。
===================================================
ドキュメンタリー映画「ガイサンシー(蓋山西)とその姉妹たち」の上映と、班忠義(Ban Zhongyi)監督のトークの催しにお誘いします。
日本在住の中国人監督による映画は、日本軍による性暴力の被害者と元日本兵の双方の証言を記録し、日本軍の性暴力犯罪が中国の寒村に残した傷 跡を記すと同時に、自らの犯した犯罪に苦しむ元日本兵の声も紹介します。
この度監督の班忠義さんがベルリンを訪問されるのに合わせて、監督のお話も伺えることになりました。
トークは日本語で行われます。ご都合がおつきになれば、ぜひお越しください。
【日時】 2014年11月14日金曜日
19時30分開始( 19時開場/本編約80分)
21時頃より、班監督を交えて質疑応答の時間をもちます。22時終了予定です。
【会場】→ AUSLAND (http://www.ausland-berlin.de )
Lychener Str. 60 10437 Berlin / +49 (0)30 44 77 00 8
最寄駅 S—Bahn Schönhauser AlleeまたはPrenzlauer Allee
【入場料】無料ですが、 会場内に班忠義監督の映画製作支援のためのカンパ箱を設置しますので、よろしくご協力ください。
【映画について】
「蓋山西(ガイサンシー)」とは山西省一の美人を意味する言葉です。日本軍による性暴力の被害者、万愛花(Wan AiHua)と侯冬娥(Hou dongE)に会おうと中国の山西省に出かけた班忠義さんは、村人から「蓋山西(ガイサンシー)」の話を聞き、その人が探していた侯冬娥だと知り ます。侯 冬娥はすでに亡くなっていましたが、班さんは侯冬娥と運命を同じくした女性たち、ガイサンシーの「姉妹たち」に出会い、10年の歳月をかけて インタビューを続け、映画にまとめました。
幼くして人生の全てを奪われた女性たちの現在の記録は、決して過去のことではありません。私たちの明日がいかにあるべきかをも示唆してくれま す。
2007年製作/ナレーションは日本語、中国語の会話には日本語字幕が入ります。
日本在住の中国人監督による映画は、日本軍による性暴力の被害者と元日本兵の双方の証言を記録し、日本軍の性暴力犯罪が中国の寒村に残した傷 跡を記すと同時に、自らの犯した犯罪に苦しむ元日本兵の声も紹介します。
この度監督の班忠義さんがベルリンを訪問されるのに合わせて、監督のお話も伺えることになりました。
トークは日本語で行われます。ご都合がおつきになれば、ぜひお越しください。
【日時】 2014年11月14日金曜日
19時30分開始( 19時開場/本編約80分)
21時頃より、班監督を交えて質疑応答の時間をもちます。22時終了予定です。
【会場】→ AUSLAND (http://www.ausland-berlin.de )
Lychener Str. 60 10437 Berlin / +49 (0)30 44 77 00 8
最寄駅 S—Bahn Schönhauser AlleeまたはPrenzlauer Allee
【入場料】無料ですが、 会場内に班忠義監督の映画製作支援のためのカンパ箱を設置しますので、よろしくご協力ください。
【映画について】
「蓋山西(ガイサンシー)」とは山西省一の美人を意味する言葉です。日本軍による性暴力の被害者、万愛花(Wan AiHua)と侯冬娥(Hou dongE)に会おうと中国の山西省に出かけた班忠義さんは、村人から「蓋山西(ガイサンシー)」の話を聞き、その人が探していた侯冬娥だと知り ます。侯 冬娥はすでに亡くなっていましたが、班さんは侯冬娥と運命を同じくした女性たち、ガイサンシーの「姉妹たち」に出会い、10年の歳月をかけて インタビューを続け、映画にまとめました。
幼くして人生の全てを奪われた女性たちの現在の記録は、決して過去のことではありません。私たちの明日がいかにあるべきかをも示唆してくれま す。
2007年製作/ナレーションは日本語、中国語の会話には日本語字幕が入ります。
→予告編

.jpg)